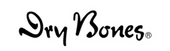2025年の8月後半、
処暑を明日に控えた22日の金曜日です。
処暑の「処」という漢字には「とめる」という意味合いがあります。
暑さがちょっと和らいでくる時期の事。
7月から続いた酷暑が、
やっとひと段落してきた感じがありますね。
夜には秋の虫である鈴虫が鳴くようになりました。
また日本のこの時期は…
終戦記念日が絡むので、
戦争について考えることが多い時期でもあります。
なので今日のブログは、
そう言ったことも含めて、
戦時衣料の代表である「チノクロストラウザーズ」についての考察。
ドライボーンズでは、
もうかれこれ35年以上作り続けている名品、
「41 khaki」という品番のチノクロストラウザーズがあります。
それがこれ、41 Khaki type Trousers。
元ネタはみんなご存知、41カーキ戦闘服。
1941年、太平洋戦争開戦時にアメリカ軍で正式採用となった、
チノクロス素材のノータックユーティリティトラウザーズ。
この写真ではマッカーサー以外が着用しています(マッカーサーは2タックが入った軍指定ではないトラウザーズ)。
後々の「チノパン」の方向性を決定づける事になるこの41カーキ、
その特徴は…
特徴的なメタルボタン(ヴィンテージにはUS.NAVYの刻印)、
緻密に作られた両玉縁ポケット、
身頃から立ち上がる一体型ウエストベルト…
繊細なウエストのダーツ、
細い細いベルトループはセンターオフセット、
ピスポケットも美しい両玉縁ポケット。
そして何より最も特徴的なのは、
この「カーキ色」。
このKHAKIの語源はインド・ヒンドゥー語の「土埃」。
1800年代初頭、
イギリスがインドを統治していた際に兵士が穿いていたトラウザーズは真っ白だったらしく…
土埃舞うインドの地では目立つし汚れるし、
兵士の間では不評だったらしい。
なので連隊長だった人物が、
その白いトラウザーズを…
カレー粉やコーヒーなどを混ぜた染料で土埃色に染めて穿いたらしい。
現地の人から「KHAKI!」と言われ、
そのままこの色が「カーキ色」で定着したらしいのです。
イギリスやフランス、オランダからアメリカ大陸に移住した人達は、
主に東海岸北部や、南西部に居を構えました。
特にイギリスから移住した人達は本国で産業革命を体感しており、
アメリカ大陸北東部に移住してから第二次産業を興したりしています。
そこにオランダ(ネイザーランド)から移住した人達も加わります。
そして時は1860年代。
北部の工業中心の勢力と、
南部の農業(綿花)中心の勢力が、
奴隷制度を発端に国を割った内戦に突入。
これがいわゆる「南北戦争」です。
イギリスから移住してきた人の中には、
インドで従軍した人達もいました。
オランダから移住した人達は、
自国のワークトラウザーズである「ニッカボッカーズ」を穿いて工場で働いていたりしました。
ここで、イギリス産「カーキ色」と、
オランダ産「ニッカボッカーズ」が融合して…
カーキ色の、裾口がスピンドルになっていて締めて穿く、
アメリカ初の「軍パン」が誕生するのです。
その後、渡り幅はニッカボッカーズ並みに太めながら、
裾のスピンドルを省いて、
渡りからストンと裾まで太いトラウザーズに省力化していきました。
北軍が勝利して終結したアメリカは…
その後スペインとの戦争にも勝利し、
フィリピンを統治することになります。
この頃はもうスピンドル無しの、
渡りから裾まで太いチノクロストラウザーズが正式採用となっていました。
その際、フィリピンから近い中国から、
大量にコットンの肉厚綾織生地を仕入れることになりました。
なので生地が「チノクロス(=中国の生地)」と名付けられたのです。
そしてドライボーンズなりに解釈して企画した、
The Civil War Type Chino-cloth Trousersがこちらです!
このトラウザーズを企画するに当たり、
当時の古着を検証しようと思っていたのですが…
1860年代の服なんて、まず今の日本では見つからない(汗)
なので、1900~1930年代くらいの欧米のヴィンテージを調べました。
共通して言えるのは…
全部の古着が渡りから裾までストンと太い。
まずは1920年代のフランス製ワークトラウザーズ。
バックストラップが付く、
センターバックがV字に切り込まれている形状。
素材はブラウンダック、
変な位置にベルトループが付きます。
そんなイメージを参照したバックスタイル。
ポケットは右側のみ。
ベルトループは現代に於いて必要なので、
オフセットしつつ装備。
こちらは1930年代のジャーマンワークトラウザーズ。
このトラウザーズのバックストラップの付け方を参照。
後ろダーツにバックストラップが挟み込まれています。
フロント部分を開けてみた図。
上部の金属フックは、
当時のオーダーメイドトラウザーズに使われていた付属。
リベットで打ってあって、質実剛健。
ポイントはボタンホール脇のパイピング。
これは…
1900年代頃のウールトラウザースを見て発案。
当時はロックミシンがまだ無いため、
この写真のように「切りっぱなし」なのです。
この仕様だと水でガンガン洗うチノパンだとちょっと厳しい。
なのでオーダーメイドのようにパイピング始末。
実に美しいチノパンの完成。
上記の様に…
「新たに作り出した古い年代設定のチノパン」なので、
ドライボーンズ製の軍パンですと、というマークを縫い付けました。
41カーキと比べて、
こんなにもシルエットが違います。
これについては先週、
マッキーがブログに書いているので参考にしてみてください。
この夏の夏っぽかった事。
地元の花火大会の直前、海岸にて。
夕焼けと富士山、そして客船の日本丸。
この後、壮大な打ち上げ花火でした。
天気が良くて最高でした!
ではまた。