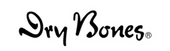2025年の啓蟄となりました。
啓蟄とは…
冬籠りをしていた虫達が土の中から出てくる頃、です。
まだ寒い日がありますが、
歯を食いしばる様な寒さからは解放されてきましたね。
ではいつもの様に、
酒丸副業の神明農場を実況中継。
遂に!
蚕豆が大量に花を咲かせました!
すごく嬉しい!
今年は特にアブラムシの害も無く、
連作障害も出ていない!
今年は大量収穫が望めそうです!
そんな朗報とほぼ同時に、
ドライボーンズの主力商品のひとつである、
DP-562が入荷したと報告が入りました。
なので本日の酒丸ブログは、
定番商品の解説をば。
再入荷してくれたDP-562とはこちら!
ジーンエンジニアリング デニムパンツ。
いわゆる、
ドライボーンズの定番中の定番ジーンズ。
ちなみにネーミングの「ジーン・エンジニアリング」
とは…
遺伝子という言葉の英訳である「GENE(ジーン)」と掛けております。
GENE ENGINEERINGが遺伝子工学なので、
JEAN ENGINEERINGでデニムパンツの遺伝子工学、
という訳です。
これがバックスタイル。
王道の5ポケット。
このポケットステッチをクローズアップすると…
このステッチは遺伝子工学を意味しており、
「DNAの二重螺旋図」を表現しております。
ここからは私の私物、
DP-562を3年くらい穿いたサンプルで解説します。
威風堂々なユーズドサンプル。
ヒゲの出方とか本当に素晴らしい(自画自賛)。
バイクや車、チャリによく乗る生活なので、
尻ぐり辺りの色落ちが一番出てます。
個人的に結構好きな部分がここ、
バックセンターオフセットベルトループ。
(ピンボケでごめん)
オフセットとは、
センターシームからずらして取り付けられている、という意味。
1950年代くらいまで、
厚手の重ね縫い部分を避けて、
この様に縫製された個体が多いのです。
また、ループセンターが一番色落ちしています。
これは、
両端を折り込んで縫う際、
センターが一番厚くなるように、
ループ専用ミシンをセットしているからなのです。
ここも好きなパーツ、
コインポケット。
このポケットだけ、
色落ちが横になります。
それはなぜかと言うと…
この様に、ポケット口に生地耳を流用したいから。
耐久性向上も含め、
生地を無駄なく使う考え方から、
この部分だけ耳利用しているのです。
脇線は生地の耳、
つまりセルビッチ利用。
この部分はヴィンテージ同様、
生地を無駄なく使うからセルビッチ利用なんですが…
当時と同じ細幅(約80cm幅)の生地を使用しているからなのです。
なぜこんなに細い幅なのか?
それは「旧式力織機」で織っているからなのです。
現在の生地、シャツ生地ならば110cm幅、
ウールなどのアウター用生地ならば148cm幅が当たり前。
現代の某有名デニムメーカーも、
152cm幅のデニムを利用してジーンズを作っています。
こう言った広い幅の生地は、
綺麗に整理整頓された糸で織られていきます。
だから早くて綺麗な仕上がりになる。
ところが力織機とは…
その名の通り「力技」で荒い糸でも織っていきます。
また戦前の織機が大半なので、広い幅に対応していない。
力技で荒々しく縦落ちしてくれる糸を織ってくれるので、
細幅デニムでの縫製にこだわりたいのです。
効率を考えたら、
152cm幅のデニムを裁断縫製した方が早くて安く作れる。
戦前の古い織機をわざわざ動かして、
荒々しい節だらけの糸をガシャーンガシャーン言いながら織られた、
ザラザラした生地を使うからこそ…
「育て甲斐のある、自分だけのデニム」になるのです。
私が3年穿いたこのヒゲ。
農作業に従事してきたからこそ出来たヒゲ、
ある意味「勲章」なのです。
ベルト付けを裏側から撮影。
下のステッチはチェーンステッチ。
チェーンステッチとは、
ある程度伸び縮みします。
つまり、ベルト部分の伸縮に身生地を合わせる為の縫製。
ところが、上のステッチはシングル本縫い。
そしてそれがどんつきまで縫われて、
直角に曲がって下に降りた後、
前立て部分に差し掛かり…
そこから鋭角に上部に戻るのです!
ここのステッチ、好き!
これはマニア間では「V字かんぬき」と呼ばれる縫製で、
下部分のチェーンステッチを押さえる役割をしているのです。
これも1960年代には消滅してしまった縫製技術。
この小股部分を裏返しにしてみた部分も、
実にマニアック。
ドライボーンズのこのデニムパンツは、
この部分の縫製が「折り伏せ縫い」という一番手間が掛かる縫製。
ほんの数センチ、僅かなこだわり。
この部分にロックミシンを使うメーカーも多いんですが…
まだロックミシンというものが開発されていなかった頃の技術を、
そのまま継承しています(遺伝子レベル)。
ここからは、
ドライボーンズのジーンエンジニアリングならではのこだわり。
まずは前立て裏。
この部分をパイピングしています。
非常に手間が掛かる縫製方法、
ドレッシーでクラシックなトラウザーズに使う方法。
こうしてパイピングにすると綺麗。
個人的に凄く拘っている部分。
もう1箇所がここ。
ピスポケットの内側。
口部分の縫製がシングルステッチなのは当然として…
ポケット布全体にスレーキを当てています。
こうする事で耐久性は2倍!
私はポケットに工具やらボルトナットやらを入れる癖があるんで…
すぐにポケット袋地が破けてしまうのです。
2倍の耐久性で、もう破ける事が無くなりました。
本当はもっともっと、
拘って作り込んでいる箇所があるんですが…
スペースの関係上、これくらいにしておきます。
まずは購入して数年間穿いてみて、
育てていってください。
色々な長所が見えてくると思います。
ではまた。
あ、そうそう、前回のブログの続き。
庭先の枝にミカンをつけて、
メジロを誘き寄せていたんですが…
来ました!!
綺麗で小さくて、
猛烈に可愛い!
メロメロです!